▲「八雲山」(須我山)
標高424.1(m) 地理院地図
『出雲国風土記』大原郡に記載されている「須我山」
山頂は開けている。
ただ、「大本八雲神社」の境内地になっているようで、その類の石碑や建造物がある。
所謂大本教である。
それを無視すれば気持ちの良い山頂である。
雲陽誌110コマp206で「須我山 【風土記】に載る所なり、古須我社ありといふ、今は諏訪明神の宮山なり、里俗寶名塚といふ、」
とあるから、須我山は諏訪神社の社地であったはずである。どういう経緯か不明なれど、大正期頃、大本に売り払ったということになる。
以下本来の山名「須我山」と記す。
(須我山)登山口案内板
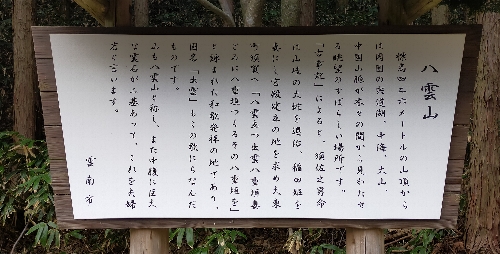
・「雲南省」と記されている。「雲南省」は中華人民共和国の省であり、「雲南市」ではない。
大本が設置したものであろう。
(須我山)山頂奥の樹林

・「寶名塚」というのは此の辺りにあったのかと思われる。
戦国期毛利氏が三笠城攻略の為、この地に番城を築いたという。「高津場番城」
(番城は特定の城主を置かず輪番で維持する城のこと)